Univocity of Mediation: Beautiful Medium

この度、parcelとNEORT++は初めての共同展として、村本剛毅による個展「Univocity of Mediation: Beautiful Medium」を開催いたします。東京を拠点に活動する村本剛毅は、アーティストとして、知覚、コミュニケーション、移動を含む「媒介」を、独自の「媒体(メディア)」を発明/彫刻するという行為によって探求しています。
本展では、複数作品を同時に公開する村本の初個展として、代表的な三つのシリーズ《Imagraph》《Lived Montage》《Training Wheels》を展開します。一連の作品は村本が実践する《媒体芸術 / Medium-Art》そのものを提起します。
あらゆるものは何かを介して移動する。 (介されるものの爆音の中で、)介するものが介することによって介する時だけに鳴らす別の音に聞き耳をたて、マーシャル・マクルーハンはメディアをメッセージと呼んだ。いつからか私の体はこの音でも震えていて、私はその音が自分によっても鳴らせるものであることに気づいた。
私の仕事は、美しいメディアを作ることである。 Meine Aufgabe ist es, ein schönes Medium zu schaffen.
この展示は、とりわけ視覚をめぐる3つのメディア — 瞼を通して閉じた眼にビデオ見せる投影機Imagraph, 同じものを見た他者と視界を映画的に共有する眼鏡 Lived Montage,指定された一文の信念を強制されながら景色を見るためのリング Training wheels — を紹介するとともに、この仕事、そして媒体芸術/Medium-Art を提起する。
《Imagraph》は、閉じた眼に対してまぶた越しに映像を投影する光学装置です。鑑賞者は目を閉じてベッドに横たわります。あらかじめ皮膚の血色を補正し青みがかった色調に変換されたビデオは、目を瞑る参加者の視界に意図された色彩とその配置と運動を伝達し、蓋は同時にまさにそれが拒もうとするものの媒体となります。閉眼という特権的な姿勢のもとで、映像の光は鑑賞者の無意識によるイメージとテクスチャーを共有して融解し、鑑賞者はどこまでが提示された映像でどこまでがそうでないのかを見失います。展示会場では、Imagraphを鑑賞するスペースに加えて、このメディアを理解するためにキュレーションされた資料・小品群《after-study for Imagraph》ーそれは作品を生み出すための習作(study)ではなく、作品を理解するために事後的に行われるstudyですーを展開します。イメージ(image)を描く(graph)装置と名付けられたこのメディアは、イメージのはじまりを連想させる奇妙な視覚体験と共に、見るもの/見せるものとして我々がもっている自由を問いただします。
《Lived Montage》は、知覚の形態として映画的モンタージュを再構築するためのゴーグル型の装置です。装置にはカメラと両眼ディスプレイが組み込まれており、参加者の目には、全員の元の視界をリアルタイムに編集した映画的な映像が投影されます。そして参加者はそれを通して空間を観察・行動し、やがてこの新たな知覚の形態に慣れていきます。本展示では、「同じものを見た全員の視界が心拍のタイミングで切り替わる」というバージョンが実演されます。動的に変容する集合的な身体と抽象的な空間認識を形成される中、「何が、何を、見ているのか」という視覚の構造に対する根源的な問いを提示されます。
《Training Wheels》は、穴の空いた真鍮の円盤とそれに一対一で対応するインストラクションによって構成された、簡素ながら詩的な作品シリーズです。手作業で片面が研磨された円盤には「すべての色はそれ自身が発光していると信じて、(何かを)見なさい」「すべてのものはすべてのものに触れたことがあると信じて、(何かを)見なさい」といったインストラクションが添えられており、鑑賞者は円盤を通して周囲の景色をみる間それに従わなければなりません。「ー(想像)しなさい」というインストラクションの形式をメディアの水準において行うこのシリーズは、媒体そのものを芸術作品とする村本の制作態度を簡潔に示すものでありながら、見るものの能動的な努力によって諸関係の鮮烈な変容を引き起こします。
本展タイトル「Univocity of Mediation: Beautiful Medium」は、メディアをメディアと呼ばせているメディエイション(媒介)が、ただ一つの同じ意味で語られるということを示しています。ここでは、人が神について語ることの可能性をめぐってスコトゥスが提起し、後にドゥルーズが差異そのものが肯定される平面として再構成した「Univocity of Being|存在の一声性(一義性)」という概念が意識されています。一義的な媒介と多様な媒体(媒介者)の差異のなかに、そして存在と媒介の差異のなかに、村本は自身の「声(voice)」を探ろうと試みています。
マクルーハンの有名なフレーズ「メディアはメッセージである(the medium is the message)」に対し、村本は端的に「このメッセージにおいて詩を書くこと」を自身の最も自然な表現行為として認め、その技術を「媒体芸術/Medium-Art」と呼びます。まさに本展は、この芸術の潜在的な系譜を読み出そうと試みる村本が、自身の作品群/媒体群を通じて、ラディカルな「媒体芸術家/Medium-Artist」像を提示する最初の機会となります。
企画:parcel, NEORT++
キュレーター協力: 多田かおり
助成: 東京大学 稲見・門内研究室, 文化庁メディア芸術クリエーター育成支援事業
Special Thanks: 藤幡正樹, 藤田結子, 森田菜絵, 原島大輔, 水野勝仁, 畠中実, 稲見昌彦, 福林開, 諏訪園佳綾
Reservation
Artist
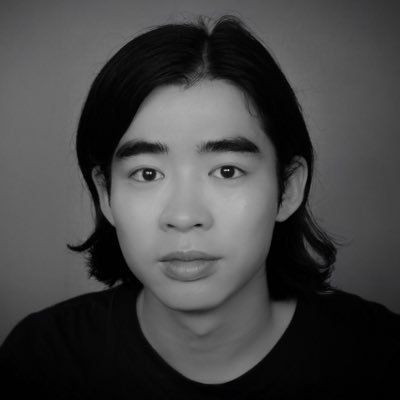
村本 剛毅|Goki Muramoto
アーティスト。1999年、山口生まれ、東京を拠点に活動。
独自の「媒体」を発明・彫刻する実践を通じて、知覚やコミュニケーション、移動を含む「媒介」について探求している。主な作品は、閉じた瞼に映画を投影する光学装置《Imagraph》series、意識する対象を他者と共有するときに視界も共有する眼鏡《Lived Montage》series、単語翻訳の連鎖を地図にした辞書/彫刻《Media of Langue》など。制作と並行して、内容に開かれた媒体そのものを芸術作品とする実践を「メディウムアート/Medium-Art」と名づけ、その理論的背景と系譜をリサーチしている。現在東京大学学際情報学府博士課程に所属。日本学術振興会特別研究員(DC1)。
Events
- ended2025.8.1 09:00 _ 2025.8.1 12:00
"Univocity of Mediation: Beautiful Medium" Opening Reception
村本 剛毅の個展 "Univocity of Mediation: Beautiful Medium"のオープニングレセプションを開催します。 予約不要でどなたでもお越しいただけます。 東京都中央区日本橋馬喰町2-2-14 maruka 3F - ended2025.8.8 09:00 _ 2025.8.8 10:30
Ecosophic Medium メディウムの美という抵抗
四方幸子On Site | YouTube
Photo: 小山田邦哉
四方幸子
十和田市現代美術館館長、美術評論家連盟会長、「対話と創造の森」アーティスティックディレクター。多摩美術大学・東京造形大学客員教授、武蔵野美術大学・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)・京都芸術大学非常勤講師。「情報フロー」というアプローチから諸領域を横断する活動を展開。1990年代よりキヤノン・アートラボ)、森美術館、NTT ICC(いずれもキュレーター)と並行し、インディペンデントで先進的な展覧会やプロジェクトを多く実現。国内外の審査員を歴任。著書に『エコゾフィック・アート 自然・精神・社会をつなぐアート論』(2023)、共著多数。 http://yukikoshikata.com - ended2025.8.8 10:45 _ 2025.8.8 12:15
The name, Media Art メディウム・アート原論
久保田晃弘 / 畠中実 | Minoru HatanakaOn Site | YouTube
久保田晃弘
多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)。近著に『遙かなる他者のためのデザインー久保田晃弘の思索と実装』(BNN, 2017)『メディア・アート原論』(フィルムアート社, 畠中実と共編著, 2018)『ニュー・ダーク・エイジ』(NTT出版, 監訳, 2018)『アナログ・アルゴリズム』(BNN, 監訳, 2024)など。
畠中実 | Minoru Hatanaka
1968年生まれ。キュレーション・批評。近年のおもな展覧会は、「多層世界とリアリティのよりどころ」(2022年)、「坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア」(2023年)、「ICCアニュアル2024 とても近い遠さ」(2024年)、「evala 現われる場 消滅する像」(2024年)など。「Ennova Art Biennale Vol.1」アーティスト選考委員(中国、2024年)、森美術館「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」アドヴァイザー(2025年)を務める。著書に、『現代アート10講』(共著、田中正之編、武蔵野美術大学出版局、2017年)、『メディア・アート原論』(久保田晃弘との共編著、フィルムアート社、2018年)。 - ended2025.8.17 08:30 _ 2025.8.17 10:00
Medium; Artwork 媒体; 作品
加治屋健司On Site | YouTube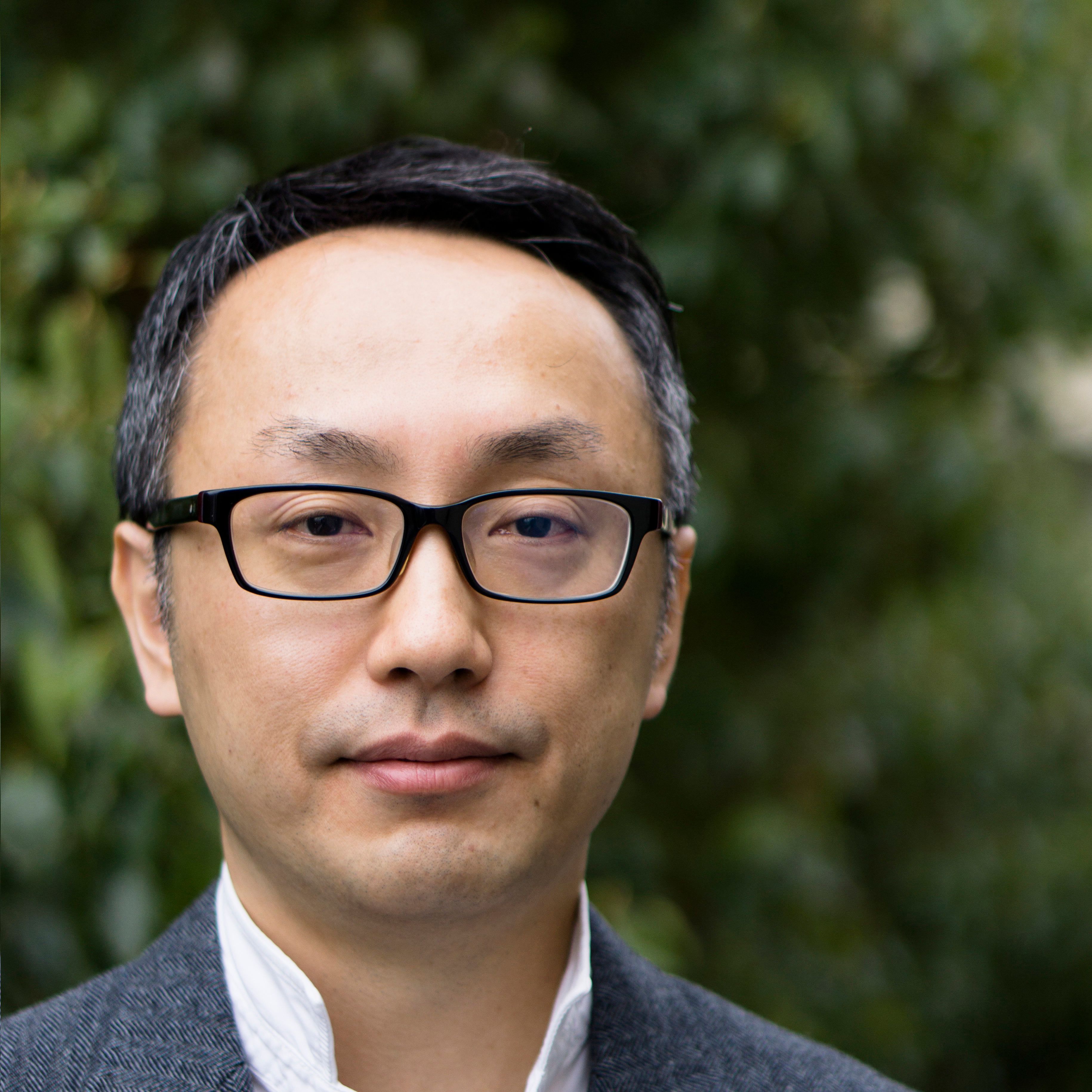
加治屋健司
1971年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科 教授、東京大学芸術創造連携研究機構 機構長。表象文化論・現代美術史。 著書に『絵画の解放 カラーフィールド絵画と20世紀アメリカ文化』(東京大学出版会、2023年)、編著に『宇佐美圭司 よみがえる画家』(東京大学出版会、2021年)、共編著に Shaping the History of Art in Southeast Asia, Art Studies, no. 3 (Tokyo: Japan Foundation Asia Center, 2017)、From Postwar to Postmodern, Art in Japan 1945-1989: Primary Documents (New York: Museum of Modern Art, 2012)、『中原佑介美術批評選集』全12巻(現代企画室+BankART出版、2011―2025年)など。 - ended2025.8.17 10:15 _ 2025.8.17 11:45
Voice of Medium Art メディウムアートの声
畠中実 | Minoru HatanakaOn Site | YouTube
畠中実 | Minoru Hatanaka
1968年生まれ。キュレーション・批評。近年のおもな展覧会は、「多層世界とリアリティのよりどころ」(2022年)、「坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア」(2023年)、「ICCアニュアル2024 とても近い遠さ」(2024年)、「evala 現われる場 消滅する像」(2024年)など。「Ennova Art Biennale Vol.1」アーティスト選考委員(中国、2024年)、森美術館「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」アドヴァイザー(2025年)を務める。著書に、『現代アート10講』(共著、田中正之編、武蔵野美術大学出版局、2017年)、『メディア・アート原論』(久保田晃弘との共編著、フィルムアート社、2018年)。




